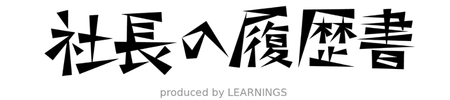今回は株式会社ベヒシュタイン・ジャパン代表、加藤正人氏にお話を伺ってきました。
「社長の履歴書」だけの特別なインタビューです。
ぜひご覧ください!
| 会社名称 | 株式会社ベヒシュタイン・ジャパン |
| 代表者 | 加藤正人 |
| 設立 | 1987年(昭和62年) |
| 主な事業 | C. Bechstein、W.Hoffmannのピアノ輸入販売(卸・小売販売) ピアノメンテナンス(調律、修理、調整等) |
| 社員数 | 34名(パート・アルバイト含む)(取材時) |
| 会社所在地 | 東京都八王子市元横山町1-12-6 |
| 会社HP | https://www.bechstein.co.jp/ |
事業紹介をお願いします
当社は世界三大ピアノメーカーの1つと称され、今年で創業170周年を迎えた、ドイツ C.ベヒシュタインの日本総代理店です。
ベヒシュタインのピアノは、リストやブラームスなど、19世紀の偉大な作曲家たちがまさに生きていた時代に生まれました。
彼らが求めた音、表現したかった感情を、形として残してきたのがベヒシュタインなのです。そのため、当時の人間が何を感じ、何を表現しようとしたのかを理解する上で、ベヒシュタインのピアノは非常に重要な存在だと考えています。
現代社会では、「正しいか・間違っているか」「早く弾けるかどうか」といった基準で音楽を捉えがちですが、芸術というのは本来そうした評価軸では測れないものです。だからこそ、私たちは「人間の芸術性をどう伝えていくか」を大切にしています。
もし正解・不正解だけを競うのであれば、高価なピアノは必要ありません。電子楽器でも、中国製の安価なピアノでも事足りるでしょう。
しかし、それでは人の感情や思想を“音”として表現することはできないからこそ、私たちはピアノを「芸術表現のための工芸品」として守り続けています。
ベヒシュタインではピアノを「芸術表現のための工芸品」として守り続けているとのことですが、具体的にどのような取り組みを行っているか教えてください
ピアノというと、日本では一般的に「工業製品」として分類されます。自動車やパソコンと同じように、工場で大量生産される製品の一つという位置づけです。
しかし、ドイツをはじめとするヨーロッパでは、ピアノはそのような“工業製品”ではありません。むしろギターやバイオリンなどと同じく、「工芸品」として扱われています。
なぜその違いが生まれるのかというと、音楽というものが単なる技術や産業ではなく、「美学」の一分野だからです。そして美学は哲学の一領域に位置づけられ、人間の内面や精神性の表現そのものと深く結びついています。
つまり、ピアノづくりとは、人間の表現を具現化する行為でもあるからこそ、私たちは“手作り”という工程を大切にしています。
そして実は、日本のピアノ産業の礎となったのもベヒシュタインでした。
日本のピアノづくりのルーツには、ベヒシュタインの技術と哲学が深く息づいているのです。
ベヒシュタインはどのように日本のピアノ産業のベースになったのでしょうか?
日本で最も大きな楽器メーカーといえばヤマハですが、そのピアノ製造の礎には、実はベヒシュタインの存在が深く関わっています。
大正時代、ヤマハの2代目社長・天野千代丸氏は「欧米のピアノづくりを学ばなければならない」と考え、技術部長の河合小市氏を中心とした視察団を欧米に派遣しました。
彼らは各地のピアノメーカーを見て回り、その中で最も理想的な製造思想と音をもっていたのがベヒシュタインでした。
これが大正10年(1921年)のことです。
その後、5年後の大正15年(昭和元年)には、ベヒシュタインの元技師長であったエール・シュレーゲル氏が日本に招かれ、ヤマハにおいて本格的な技術指導を行いました。
この時、ヤマハは「日本国内でベヒシュタインを販売する」という契約を結び、その代わりに製造技術の提供を受けたといわれています。
シュレーゲル氏は約5年間、浜松に滞在し、日本人技術者にピアノ製作のノウハウを直接伝えました。
これが、日本のピアノ産業が本格的に開花していく原点となったのです。
当時、日本の音楽教育や演奏家が慣れ親しんだピアノの音、それがまさにベヒシュタインのサウンドでした。だからこそ、戦前の時代に多くの音楽家たちが「理想の音」として思い描いていたのは、ベヒシュタインが生み出す響きだったのです。
私たちがいま伝えたいのは、まさにその「原点に立ち返る」ということです。
100年前の日本人が、どのような音を美しいと感じ、何を表現しようとしていたのか。
その感性をもう一度思い出し、頭と心の両方を使ってピアノと向き合うことの大切さを、ベヒシュタインを通じて伝えていきたいと考えています。
ベヒシュタインのピアノの魅力を教えてください
ベヒシュタインの魅力は、何よりも「音楽の会話性」にあります。
ヨーロッパの教授を招いて公開レッスンを行うとよく感じるのですが、音楽というのは単なる音の連なりではなく、“語り合い”そのものなんです。
例えば、女性の声が語りかけ、それに男性の声が呼応する。そうした“対話”がハーモニーを生み出し、一つの情景を作り上げていく。音楽の中には、そうした人間的な会話のような流れがたくさん存在します。
その会話の背後には伴奏があり、伴奏もまた単一の音色ではなく、複数のレイヤー(層)で構成されています。
オーボエのような音色、フルートのような透明感、弦楽器の響き……ショパンやブラームスといった作曲家たちは、そうした多層的な響きを楽譜に書き込んでいます。そして、その繊細なレイヤーの違いを最も自然に表現できるのが、ベヒシュタインのピアノなのです。
音量や派手さを競うのではなく、作曲者の意図をどう伝えるか。演奏者が自らの感性を、音楽そのものにどこまでコミットできるかが重要です。ベヒシュタインのピアノは、その“表現力の深さ”において他に類を見ません。
演奏者が伝えたい感情を、まっすぐに音として表現できる。だからこそ、音楽家にとってこれほど心強い楽器はないと感じます。
また、ベヒシュタインは「音量」ではなく「音楽性」を追求しています。
たとえば、家庭で練習する際に求められるのは大音量ではなく、音の表情をどこまで作り込めるかです。そのため、ベヒシュタインのピアノはグランドピアノだけでなく、アップライトピアノや小型グランドピアノの評価が非常に高いのも特徴です。
音の大きさではなく、音楽性を育むトレーニングができる――それこそが、ベヒシュタインが世界中で愛される理由です。
音量よりも表現力や音色の多層性を重視し、「音楽性を引き出すトレーニングができる楽器」として設計されており、かつその思想が、次世代を担う若い演奏家たちにも確実に受け継がれつつあります。
ベヒシュタインのピアノの魅力については、下記URLをご参照ください。
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsqd1mH4-BlFH2IZXSjRgQg
おすすめの動画はこちら→「なぜベヒシュタインの音色は真似できないのか?加藤社長が語るベルリンでの修行時代に学んだ門外不出の製造レシピ」
Instagram:https://www.instagram.com/c.bechstein_japan
Facebook:https://www.facebook.com/bechsteinjapan/
X:https://twitter.com/bechstein_japan
ここからは加藤社長のことをお聞かせください。学生時代に打ち込んだことはありますか?
学生時代は、理系の分野にも強い関心を持っていました。
特にアマチュア無線に夢中で、友人たちと一緒にアンテナを組み立てたり、屋根にアンテナを張ったりしながら、電波を飛ばして通信することに大きな興味を抱いていました。
自分で無線機を一から作るのは難しかったのですが、簡単な電子回路を組んで試すなど、技術的な工夫を楽しんでいましたね。
同時に、音楽もずっと好きで、バンドを組んでいました。実は、幼い頃にピアノを習っていたのですが、私の地元・岐阜県多治見市のような地方では、当時、男の子がピアノを習うというのはまだ珍しい時代でした。
そのため、一度はやめてしまったのですが、音楽への思いは消えず、後にもう一度自分からピアノの先生のもとへ通い直しました。
高校に入ってからも、趣味として再びピアノに向き合うようになり、そこから少しずつ「音づくり」への関心が深まっていったように思います。
調律師を目指されたきっかけを教えてください
高校時代は理系クラスに所属しており、周囲の友人たちは難関大学や医学部を目指して勉強に励んでいました。
彼らの努力や競争を見ながら、「自分は何をしたいのか」「何に向いているのか」を改めて考えたのが高校3年生のときです。
偏差値を少しでも上げて良い大学を目指すという道もありましたが、本当に自分が打ち込みたいのは“好きなことを活かす生き方”ではないかと感じました。もともと理系的なものづくりが好きで、同時に音楽にも強い関心があった私は、「この二つを融合できる分野はないだろうか」と考えました。
そんなとき、進学情報誌で偶然目にしたのが、国立音楽大学のピアノ調律科でした。そこには「ピアノの設計」「音の構造」といった言葉が並んでおり、「これだ」と直感しました。音楽と理工学的な要素が交差する世界に、自分の得意分野を活かせるかもしれない。そう思ったのです。
親からは「もし受からなかったら諦めなさい」と言われていましたが、幸いにも合格することができました。そこから、ピアノの内部構造や音響、設計思想にのめり込み、自然と“調律”の世界に進むことになりました。
結果的に、この選択が後の人生を決定づける大きな転機になったと思います。
ちなみに、当初からヨーロッパに渡ることは考えていらっしゃったのでしょうか?
国立音楽大学で学ぶ中で、次第に「ヨーロッパでピアノづくりを本格的に学びたい」という思いが芽生えました。私の恩師が日本女性で初めてドイツのマイスター資格を取得された方で、「自分もいつかはヨーロッパの現場で本物を学びたい」と考えるようになったのです。
とはいえ、その時点ではまだ「いつか行けたら」という程度の思いでした。
そのため、卒業後は放送局のピアノ保守や調律を請け負う会社に入社しました。
そこでは、テレビ番組『ザ・ベストテン』や、武道館で行われるコンサートで使われるピアノの調律を任されたりと、華やかな舞台裏に立ち会う機会が多くありました。若い頃は、芸能人や著名なアーティストと関われることが純粋に楽しく刺激的でしたが、次第に“慣れ”が生まれるとともに、心の中で違和感が芽生えました。「自分が本当にやりたかったのは何だったのか?」と思い返せば、私がこの道に入った原点は、ピアノの“設計”や“構造”への関心にありました。
目の前の調律だけでなく、ピアノという楽器そのものの仕組みを深く理解し、作る側に回りたい。そう考えるようになり、“本場ドイツで学び直そう”と決意しました。
ドイツではマイスター資格をとるために修行をされていましたが、振り返って良かったと思う経験を教えてください
ドイツでマイスター資格を取得するための修行を振り返ると、技術面だけでなく、経営や社会に関する学びが大きな財産になったと感じます。
マイスター制度というのは、ピアノ製作だけでなく、醸造、服飾、靴づくりなど、あらゆる分野の職人が対象です。そして共通して求められるのは、「自ら工房を構え、弟子を育てながら経営できること」です。つまり、マイスターとは単なる“熟練の職人”ではなく、“職業人として社会を回すリーダー”でもあるわけです。
そのため、試験科目には専門技術だけでなく、簿記や会計、税法、労働法といった幅広い分野が含まれています。
たとえば、勘定科目の振り分けや貸借対照表の作成、手形の裏書きといった実務的な内容も学ばなければなりません。また、工房の運営に必要な法律(労働法、社会法、商法など)も理解しておく必要があります。これらの学びは、一見ピアノづくりとは関係がないように思えますが、職人として生きていく上では欠かせないものでした。自らの技術を社会の中でどう活かすか、どう持続させるか。その根幹を支える「経営感覚」を身につけられたのは、マイスター修行の中でも特に大きな成果だったと感じています。
ドイツでマイスター資格を取れば、ドイツでそのまま働いて自身の工房を持つこともできたなか、どうして日本に帰国されたのでしょうか?
仰る通り、マイスター資格を取得した後、そのままドイツで働き続ける道もありました。しかし、私の場合は結婚しており、家族を伴っての留学生活でした。下の子はドイツで生まれ、上の子はちょうど幼稚園を卒業して小学校へ上がる時期。これから子どもをどのような環境で育てていくかを真剣に考えたとき、人生設計を見直す必要があると感じたのです。
もしこのままドイツで暮らし続ければ、子どもは現地の小学校に通い、そのままドイツで育つことになります。そうなると日本へ帰国するのは、大学進学のタイミングになるでしょう。インターナショナルスクールという選択肢もありましたが、私自身は「現地の公教育で学ばせるか」「日本に戻るか」という二択で考えていました。そして最終的に、「やはり日本で生きていく基盤を築こう」と決断しました。
そもそも私がドイツへ渡った目的は、現地で経験を積み、技術と哲学を吸収したらそれを日本に還元していくことだったので、マイスター資格を取得した時点で、次のステージに進むタイミングだと感じました。
ドイツで学んだピアノづくりの思想や技術を日本の音楽文化に活かしていくことこそ、自分の使命だと考えました。
ベヒシュタイン・ジャパンにご入社されて、技術実務だけでなく営業もされてらっしゃったとのことですが、どのような経緯でこの2つをやっていくことになったのか、教えてください
一見するとまったく異なる分野のようですが、ベヒシュタインというブランドにおいては、技術を理解したうえでお客様に伝える力が何よりも重要です。
ベヒシュタインのピアノは、工業製品ではなく一つひとつが手作りの“工芸品”であるため、単に販売トークや営業スキルだけで説明しようとしても、ピアノの魅力はなかなか伝わりません。
お客様が「なぜ音が違うのか」「どのように作られているのか」と疑問を抱いたときに、それをきちんと構造や製造思想のレベルで説明できる人でなければ、納得していただけないのです。
実際、ドイツのベヒシュタインの店舗でも、責任者は多くがピアノ技術者や演奏家です。もちろん、財務やマーケティングに長けたパートナーがサポートしているケースもありますが、お客様と直接向き合う販売の中心にいるのは、ピアノを深く理解している人たち。
それがベヒシュタインの文化でもあります。
ですから、私自身も調律師としての専門知識を活かしながら、お客様にベヒシュタインの音の魅力や構造の違いを伝えることを意識して営業活動をしてきました。
「売る」のではなく、「伝える」。この姿勢こそが、ベヒシュタインの価値を守り続けるために最も大切なことだと考えています。
社長就任の経緯を教えてください
社長就任の打診があったのは、実際に就任する1年ほど前のことでした。
当時の私は、技術や製造、現場には長く関わっていましたが、経営に関する分野に強い自信があったわけではありません。
そのため、最初は「自分には難しいと思います」とお断りしました。しかし、その後も本社や関係者から何度か打診を受け、最終的には3度目の要請で決心しました。
社長就任のきっかけを一言でいえば、「ベヒシュタインというブランドを最も理解している者としての責任」でした。
私は長年にわたり技術者として、そして営業の現場でも、ベヒシュタインのピアノと向き合ってきました。
“誰よりも”とは言いませんが、この楽器の構造や音づくり、そしてブランドの哲学を深く理解している一人であるという自負はあります。
そのため、当時の状況やタイミングを考えたとき、「自分がやらなければ、誰がやるのか」という気持ちが強くありました。
また、ちょうどその頃、ドイツ・ベルリンの本社からも「今こそあなたが率いるべきだ」という後押しをいただいたことも大きかったです。もちろん、経営や財務の専門家、マーケティングのプロフェッショナルは他にもたくさんいます。しかし、ベヒシュタインの“本質”を理解し、それを正しく日本の市場に伝えられる人間となると、数は限られていました。
ベヒシュタインというピアノは、単に高価な楽器というだけではなく、“音楽という芸術をどう捉えるか”という哲学そのものを体現しています。その理念を守り、正しく伝えることこそが私の使命だと思い、社長としての役割を覚悟を持って引き受けました。
ヨーロッパと日本ではピアノの商習慣が異なるのでしょうか?
ヨーロッパと日本では、ピアノを取り巻く環境や商習慣が根本的に異なります。
日本の場合、私たちがよく目にするのは「ヤマハ音楽教室」や「カワイ音楽教室」など、メーカー主導の教育システムです。
つまり、楽器メーカーが自社のマーケティングや販売促進の一環として音楽教育を提供しており、その仕組みの中にピアノ販売が位置づけられています。
一方、ドイツをはじめとするヨーロッパでは、音楽教育の土壌がまったく違います。
メーカーが運営する教室ではなく、市や自治体が運営する「音楽学校(Musikschule)」が一般的で、たとえば「〇〇市音楽学校」のような形で地域に根ざしています。子どもから大人まで、住民が音楽を学び、楽しむ場として存在しており、そこに自然とピアノや講師、調律師といった専門家が関わっているのです。
この違いは、単なる販売方法の違いではなく、音楽の捉え方そのものの違いにあります。
ヨーロッパでは「たくさん楽器を売るための教育」ではなく、「音楽を楽しむための教育」が根づいており、販売もその延長線上にあります。そのため、19世紀の頃からピアノの販売は、単なる営業職ではなく、ピアノ技術者や演奏家が担うものとして発展してきました。
つまり、「技術と芸術の橋渡しをする人」が楽器を届けていたのです。
一方日本では、長くメーカー主導のマーケティングが中心でしたが、近年では次第に「ピアノの本質」や「表現の幅」に関心を持つ人が増えてきています。
アコースティックピアノは消耗品ではなく、長く使い続けるものです。だからこそ今後は、“売る”というよりも、“ピアノという文化を啓発していく”という姿勢が大切になると感じています。この点で、日本とヨーロッパの間には土壌そのものの違いがあると言えるでしょう。
経営者として仕事をするなかで、どのような苦労がありましたか?
就任して間もなく、新型コロナウイルスの感染拡大が起こりました。
ベヒシュタイン本社との資本提携を終え、「これから新しい展開を」と思っていた矢先の出来事で、まさに想定外のスタートでした。
音楽教室は一時的に休業、外出制限もあり、コンサートやイベントなど人を集める活動がすべて止まり、経営者としても、会社としても非常に厳しい時期でした。ただ、興味深いのは、ロックダウン後に「楽器の特需」が起こったことです。
旅行や外出が制限された分、「家の中でできること」として音楽を再び始める人が増え、ピアノを購入する方も目立ちました。
もちろん、ベヒシュタインのような高級ピアノが一気に売れるわけではありませんが、一度落ち込んだ市場が想像以上のスピードで回復していったのです。
しかし、マーケティング面では大きな制約がありました。従来行っていた「レクチャーコンサート」や「公開レッスン」といったイベントは、人を集めること自体が難しくなり、“音楽に人を集める”という行為が一時的に“罪悪感”を伴うような空気になりました。
オンライン化も進みましたが、ピアノの魅力は画面越しでは伝わりにくいものです。音の立体感や質感を体感してもらうことができず、非常にもどかしい時期が続きました。ようやく人を集めて開催できるようになったのは、ごく最近のことです。
そして現在は、新たな課題として為替の影響があります。ピアノはすべてユーロ建ての輸入品のため、円安が進むと仕入れコストが直撃します。これに関しては本社からもサポートを受けつつ、価格調整や経営バランスをどう取るかという難しい判断が続いています。
経営者としての苦労は絶えませんが、その都度「音楽文化をどう守り、どう伝えるか」という原点に立ち返りながら、前に進むようにしています。
組織運営ではどのようなことが大変でしたか?
経営者として実際に組織のトップに立ってみて最も難しいと感じたのは「人の心を掴むこと」でした。
どれだけ丁寧に伝えたつもりでも、言葉がそのままの意味で受け取られないことがあります。
意図が誤解されたり、背景まで正確に伝わらなかったり――。この「伝えることの難しさ」は、どんな時代のリーダーも苦労してきたのではないかと思います。
私自身、稲盛和夫さんの著書などでリーダーシップとは何かを学び直していますが、やはり最終的には“人を動かすのは理屈ではなく信頼”だと思います。だからこそ、コミュニケーションエラーを減らすための仕組みづくりが重要だと感じています。
個々の問題というよりも、組織としての情報共有の構造が整っていないことが原因で起こるすれ違いも多いので、そこを一つずつ整備していくのが、いまの課題の一つです。
また、よく「朝令暮改は当たり前」と言われますが、私自身は簡単に方針を変えることに抵抗があります。
ピアノという商品は、電化製品のように数年単位でモデルチェンジを繰り返すものではありません。何十年というスパンで人の生活に寄り添う楽器だからこそ、一貫性を持ち、長い目で見たブランドの方向性を守ることが大切だと考えています。
だからこそ、ベヒシュタインの理念をぶらさず、時間をかけて社員やお客様と共有していく。その姿勢を大切にしています。
組織運営において、加藤社長が心がけていらっしゃることはありますか?
経営者として組織を運営するうえで心がけているのは、自分の得手・不得手を正しく理解することです。
私は技術畑出身ですので、マーケティングや財務といった分野は必ずしも得意ではありません。だからこそ、それらの領域を信頼して任せられる人にサポートしてもらうことが大切だと考えています。
自分がすべてを完璧にこなすのではなく、組織として力を発揮できる体制を整えること。そのために、専門性を持ったスタッフの意見を積極的に取り入れ、お互いの強みを生かし合える仕組みづくりを少しずつ進めています。
人に頼ることは決して弱さではなく、チームとしての成長のために必要な姿勢だと思っています。まだ道半ばではありますが、そうした体制を築いていくことが、結果的に社員の自立と成長にもつながると感じています。組織としてより強く、柔軟に動けるようになること。それがいま目指している方向です。
今後の展望について教えてください
現在、私たちは東京・日比谷という一等地にフラッグシップショールーム「ベヒシュタイン・セントラム東京」を構えています。
これはドイツ本社との強い協力関係のもとで実現したものであり、今後はここを起点に、より消費者に近い形での小売展開を強化していきたいと考えています。
これまでの日本市場では、販売の多くがディーラー経由でした。もちろんその仕組みを否定するつもりはありませんが、今後はベヒシュタインの理念や価値観を深く共有してくださるパートナーとともに、「同じ目線で市場に広げていく」ことを重視していきたいと思っています。単に販売チャネルを拡大するのではなく、「ブランドを正しく伝えてくれる仲間を増やすこと」が、次のステップだと感じています。
また、ピアノ市場全体の中で見れば、日本におけるベヒシュタインの新品出荷シェアはまだ2%程度です。ドイツ国内では約30~40%のシェアを持つことを考えると、ここには大きな伸びしろがあります。将来的には、日本でも10%程度まで拡大できるよう、着実に基盤を整えていきたいと考えています。
最近では、コンサートホールの在り方も変化しつつあります。これまで“スタンウェイ一択”という風潮だったところに、「自分たちのホールの個性を出したい」「違う響きを持つピアノを置きたい」と考えるホールが増えてきました。実際に、ベヒシュタインを採用したいと考えてくださっているホールも増えていますので、そうした音の多様性を尊重する動きは、これからさらに広がっていくと思います。
今後も、ベヒシュタインが“選ばれるブランド”であり続けるために、単にシェアを追うのではなく、音楽文化そのものを支える存在として、日本の市場により深く根づいていけるよう努めていきたいです。
他の経営者におすすめの本のご紹介をお願いいたします
もし一冊ご紹介するなら、ぜひ弊社の書籍である『“私の”ベヒシュタイン物語 ~エッセイコンテスト公募作品・委嘱作品集~』(戸塚亮一 編)を手に取っていただきたいと思います。
この本は、音楽雑誌『ショパン』を発行している出版社・ハンナより刊行したもので、ベヒシュタインのピアノを愛用されている方々のエッセイを集めた作品集です。前社長であり創業者の戸塚亮一が監修を務め、私自身も一編を寄稿しています。それぞれの方がどんな思いでベヒシュタインのピアノを弾いているのかという、単なる楽器を超えた“人生の物語”が綴られています。
読むたびに、音楽が人の心にどれだけ深く寄り添うものかを改めて感じさせられる一冊ですので、経営者の方にも、ものづくりやブランドづくりの原点を考えるヒントになると思います。
ぜひご一読ください。
| 『“私の”ベヒシュタイン物語 ~エッセイコンテスト公募作品・委嘱作品集~』 戸塚 亮一 (著, 編集) |
投稿者プロフィール


-
企業の「発信したい」と読者の「知りたい」を繋ぐ記事を、ビジネス書の編集者が作成しています。
企業出版のノウハウを活かした記事制作を行うことで、社長のブランディング、企業の信頼度向上に貢献してまいります。
最新の投稿